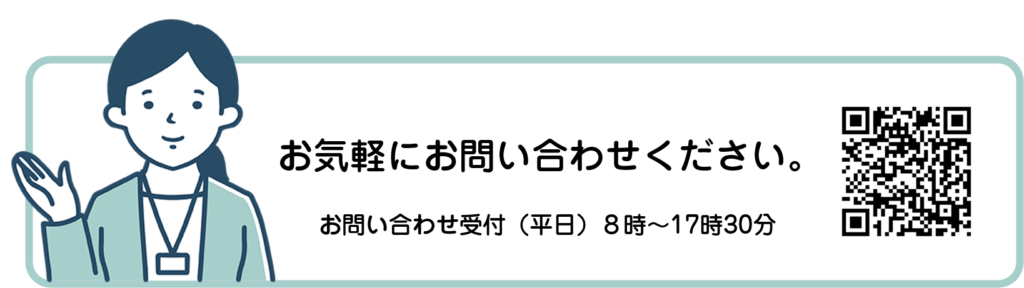- ピックアップ
- 精神科デイケアにおけるWRAPプログラムの取り組み
2025年10月01日
精神科デイケアにおけるWRAPプログラムの取り組み
〜アルコール依存症・統合失調症へのリカバリー支援〜
南山病院の精神科デイケアでは、当事者が自らの「元気でいる方法」を見つけ、再発予防と生活の質の向上を目指す自己管理プログラムであるWRAP(Wellness Recovery Action Plan)を導入しています。
このプログラムは、アルコール依存症や統合失調症といった異なる精神疾患を抱える方々にも、それぞれの課題に応じた柔軟な対応が可能であることから、現在は両疾患の方々を対象に同時展開しています。
又、当法人では「WRAPファシリテーター養成研修」を受講した有資格者による専門的な支援のもと、質の高いプログラム運営を行っています。
WRAPとは?
WRAPは、1997年にアメリカのメアリー・エレン・コープランド氏によって開発された、リカバリー(回復)を目指すための個別計画です。特定の治療方法ではなく、当事者自身が「自分の元気を保つ方法」や「ストレスへの対処法」「早期警告サインへの対応策」などを考え、記録し、活用していくプロセスが中心です。
WHO(世界保健機関)も、WRAPのようなリカバリー支援モデルが、精神保健福祉における当事者中心のアプローチとして有効であることを提言しています[WHO, 2013]。

デイケアでの実施の意義
精神科デイケアは、医療と生活支援の中間的な場として機能し、日中の安定した生活リズムや社会的交流の機会を提供します。これにWRAPを組み込むことで、利用者が自分自身と向き合い、他者と共有しながらリカバリーのプロセスを実感しながら歩むことができます。
このプログラムは、社会生活場面でさまざまな環境やストレスに触れているデイケア利用者にとって有意義であり、自己管理能力を高める支援となります。
当院では、週1回、1回60分程度のWRAPプログラムを実施し、3ヶ月単位で1サイクルを完結としています。
プログラムは以下のような構成です。
・日常生活での「元気のための道具箱」づくり
・体調変化に気づく「引き金・早期警告サイン」の整理
・危機時の対応計画(クライシスプラン)作成
・他者との共有を通じたリカバリーの気づき
・クライシス後の対応と支援
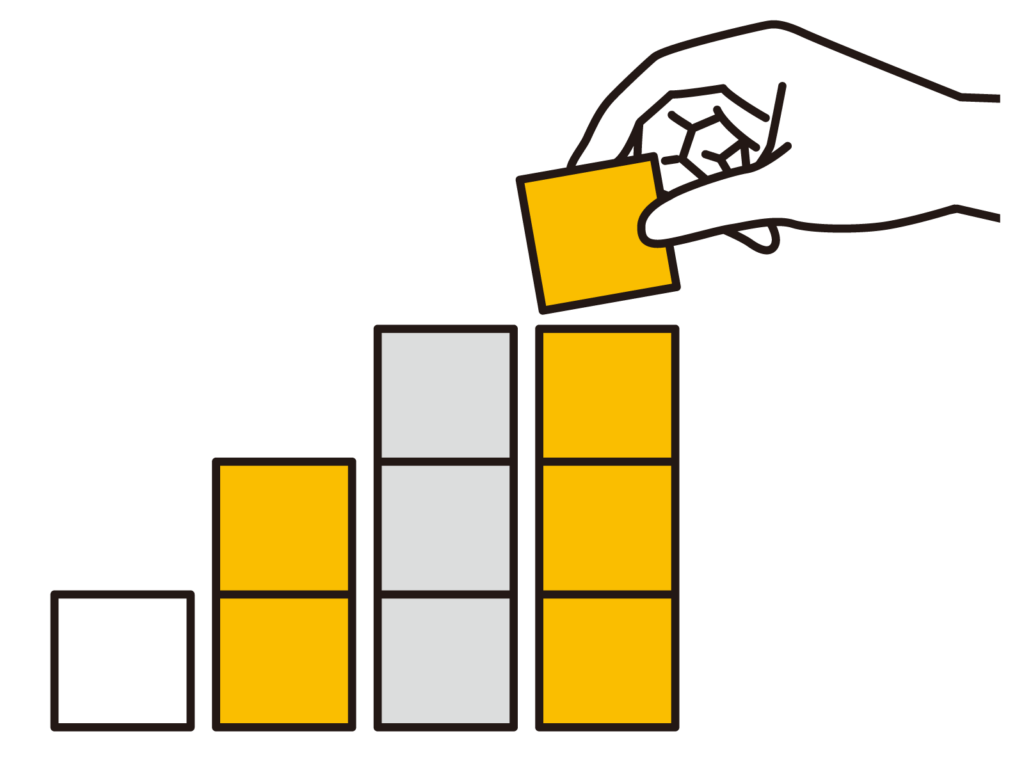
アルコール依存症とWRAP
アルコール依存症は再飲酒の予防が課題であると同時に、「やめ続けること」が大きな課題です。WRAPでは「飲酒欲求が高まるときの自分の状態」や「飲まないための支援策」「再発時の立て直し方法」などを当事者自身が考え、日常に活かすことで再発予防への意識向上と生活の再構築に有効です。又、これまでのストレスをアルコールという物質回避で代替していた当事者にとって、リカバリーを考えていく事は時に困難さを伴う場面もありますが、アルコールに依存せずに生きるための主体性を高めることを目的としています。
例えば、参加者の中には「飲酒を誘われやすい場面を避ける具体的な行動」や「飲まずに過ごせた日の自分の感覚」を言語化することで、自信を回復していった方もいます。WRAPを通じて、自助グループや支援者とのつながりを再確認するきっかけにもなっています。
統合失調症とWRAP
統合失調症では、幻覚・妄想などの症状が再燃しやすく、また自己肯定感の低下も課題になることもあります。WRAPでは、「調子のよい時の自分」を明確にし、「悪化のサイン」や「ストレス要因」に気づくことで、再発の予兆を早期にキャッチする力が養われます。
また、罹患期間や入院期間で失われた「やってみたい」というアイディアをWRAPプログラムを通して具体的に体験する事でこれまで成し得なかった当事者自身の新たな体験の発見にもつなげていきます。
さらに、「自分でできる対処法」を増やすことで、自立した生活への希望や目標が生まれやすくなり、社会復帰を目指す上での精神的な支えになります。WRAPの集団ワークでは、他の参加者の回復のストーリーに触れることができ、それが大きな励みとなることも特徴のひとつです。
同時展開の工夫と効果
WRAPは「疾患名」ではなく、「本人の体験」に基づくプログラムのため、アルコール依存症と統合失調症の方が同じ場で語り合い、学び合うことが可能です。ただし、それぞれの特性に応じた支援が求められるためグループ分けをしたり、個別支援と並行して進めたりする柔軟な運営も大切にしています。
こうした取り組みを通じて、当事者主体の回復モデルが持つ力を体感しやすくなり、自らのリカバリーに前向きに取り組む意欲を高めることができます。
【まとめ】リカバリーは「自分で選ぶ回復の道」
沖縄県糸満市にある南山病院では、WRAPの実施を通じて、「リカバリーは医療だけではなく、当事者自身の力に支えられている」ことを改めて実感しています。WRAPは診断名や重症度に関係なく、児童思春期を含むすべての年齢層の方が「自分らしい回復の形」を見出すための道具となります。
このプログラムを通して、職員もリカバリーの本質を深く理解し、その支援のあり方について考える機会を得ています。当事者自身のリカバリーを通して、職員が介入しながらエンパワメントを考えていく事とその介入の影響で当事者の未来に不利益がないように、スタッフが横並びで支える事の本当の意味での大切さの難しさを痛感しています。この課題と向き合いながら、より良い支援を提供できるよう努めてまいります。 今後も当院では、沖縄という地域性を踏まえながら、多様な精神的困難を抱える方々が自らの人生に希望を見いだせるよう、WRAPをはじめとする参加型プログラムを継続・発展させてまいります。
医療法人陽和会南山病院 リハビリ部
デイケアセンター長 仲村 翼