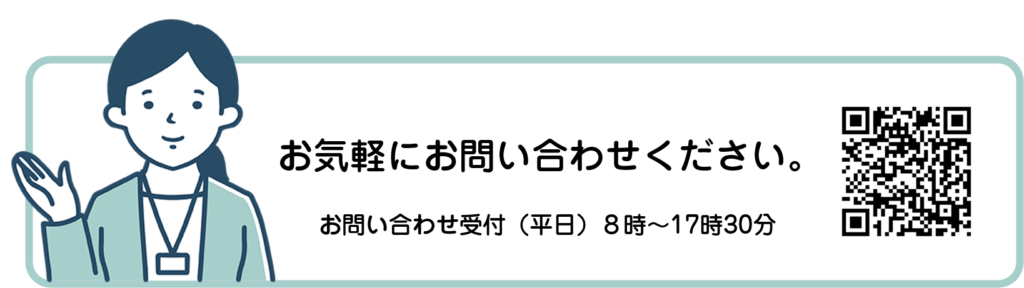- ピックアップ
- [前編]発達特性を知ることは、自分を守る力になる
2025年11月01日
[前編]発達特性を知ることは、自分を守る力になる

児童思春期外来のご紹介
「発達障害」という言葉を聞いて、何を思い浮かべますか?
「成長が阻害されている」「他の子どもができることができない」——そんなマイナスなイメージを抱く方も多いかもしれません。しかし、発達障害とは、得意・不得意の差が大きく、特性のあらわれ方が変化する“脳のタイプ”であり、固定された障害ではありません。
2013年に米国精神医学会が発行した『DSM-5』では、「神経発達症」という呼称が採用され、その後使用されることが増えてきました。これは、発達特性の表れ方が固定的ではなく、遺伝と環境の相互作用によって強まったり弱まったりする流動的なものであること、また、特性の程度にはグレーゾーンも含めた個人差(スペクトラム)があり、「ある・ない」と線引きできるものではないことなどが理由にあげられます。
たとえば、神経発達症の一つである自閉スペクトラム症では、思考の偏りや、他人の言葉を字義通りに受け取る傾向、境界線を引くことの難しさなどが、人間関係を築くうえで障害となることがあります。かつては、こうした特性が「本人の努力不足」や「親のしつけの問題」とされていた時代もありましたが、実際には脳の特性によるものです。したがって、無理に社会に適応させるのではなく、自分を知り、得意な分野を伸ばし、自分に合った環境を選べるようにすることが大切です。
診断を受けることは、自分を知る第一歩であり、自分の特性を自覚することは、将来の自分を守るためにも重要です。
日本社会には競争的な側面が多くあります。「学校は毎日行くもの」「将来、週5日働くためには今から毎日登校しなければならない」そんな思い込みにとらわれている子どもたちも少なくありません。教えられたことを過剰に意識し(字義通りに受け取り)、適応しようと努力しているお子さんも多いのではないでしょうか。しかし、特性によって集団活動に強い疲労を感じる場合は、自分のペースで休みを取り入れることも良い環境調整になります。大人になってからも、競争社会に煽られ、自分に合わない環境で疲弊してしまうことがあります。だからこそ、「どんな環境が自分に合っているか」を認識し、「自分に合った環境を自ら選び取る力」を育むことが大切です。
受診前には、お子さんの困った行動の理由がわからず、親御さん自身が「自分の育て方が悪かったのでは」と悩まれていることもあります。しかし、お子さんの全体像を把握すると、「今の困りごとは、子どものせいではなく、特性や環境とのミスマッチが背景にあること」「親が悪いわけではないこと」が見えてくることが多いです。
私たちは、お子さんや親御さんと評価を共有し、納得していただいたうえで、学校や友人関係が少しでも楽になるよう、味方として支援します。また、親御さんには子育ての方針を一緒に考える時間を設け、安心と希望を持っていただけるよう努めています。
南山病院 児童思春期外来
子どものこころ専門医 山口 一豪