

- ピックアップ
- 児童思春期の自傷行為とその背景
2025年09月01日
児童思春期の自傷行為とその背景
~ 地域で働く精神科医として思うこと ~
当院では2019年から児童思春期外来を開設し地域の子どもたちの心のケアに取り組んできました。児童思春期の担当医として働く中で、自傷行為に直面する機会は少なくありません。南国の穏やかな風景の中にも、子どもたちの心の痛みは確かに存在し、私たち医療従事者はその声に耳を傾ける責任があります。
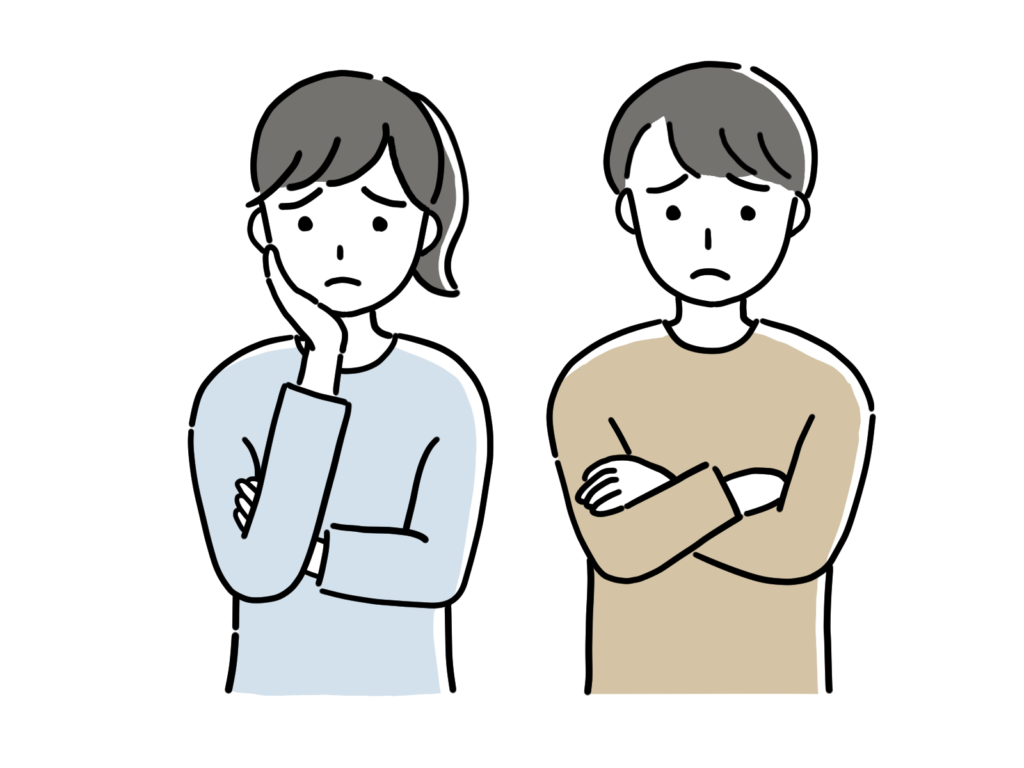
自傷行為は「心の叫び」
自傷行為とは、自らの身体を傷つける行為です。リストカット、オーバードーズ、抜毛など、その形はさまざまですが共通しているのは「言葉にできない苦しみ」を表現しているという点です。
糸満市をはじめとする沖縄の地域社会では、家族や近隣とのつながりが深く、互いに支えあう文化が根付いており、協調性が必要となります。そうした環境は「人に迷惑をかけないように」「自分の気持ちは自分で整理する」といった内面的な強さが求められる環境でもあり、元々、人間関係が苦手な子ども、自己肯定感の低い子どもたちにとっては苛酷な環境となりえます。その結果、心の中に抱えた葛藤や不安が、自傷という形で表現されることもあります。
背景にある要因
私たちが診察室で出会う子どもたちの多くは、以下のような背景を抱えています。
◆学校内の不和や困窮で安心できる居場所を失っている。
◆小中学校での人間関係のトラブルは、孤立になりやすく自尊心を大きく傷つけます。
いじりや、からかいといった行動が結果としていじめに繋がることもあります。特にSNSを通じたいじめは、大人が把握しずらく本人の孤独感を深めます。
◆ADHDやASDなどの発達特性を持つ子どもは、感情のコントロールが難しく、衝動的な行動が多くなりがちです。周囲からの孤立や大人からの叱責を受けやすく、柳うつが強まり自傷行為に及ぶことがあります。
地域医療としての支援のあり方
糸満市をはじめとする沖縄の地域では、温かな人間関係や支え合いの文化が根付いており、子どもたちもその中で育まれています。そうした地域の力を活かしながら、児童思春期の心のケアに取り組むことが、私たち精神科医の大切な役割です。
医療機関だけでなく、学校や家庭、地域の保健師、スクールカウンセラーとの連携を通じて、子どもを取り巻く環境全体に働きかけることが求められています。診察室の中だけでは見えない子どもたちの生活や心の動きに寄り添うために、私たちは家族面談だけではなく地域のエンパワーメントを取り入れ子どもたちを支える環境を構築しています。
われわれ大人が、自傷行為を「問題行動」として捉えるのではなく、本人が抱える苦しみや不安の表現であること、その行為自体が「心のSOS」であり「生きたい」というメッセージであることに気づき、地域全体で支え合う視点を共有することで、子どもたちが安心して自分らしく生きる力を取り戻す支援に繋がると信じています。
自傷行為を目にしたとき、大人は驚きや恐怖、怒りを感じるかもしれません。何とか辞めさせようと叱責したり、優しく論したり、冷静に説得を試みたりと、試行錯誤することでしょう。大人も苦しくなると思います。ただ子どもたちは「助けて」と言えない代わりに、身体を傷つけることでその思いを伝えようとしているのです。私たち医療者は、診断や治療だけでなく、子どもたちはもちろん、親をはじめとする大人たちも、みな同じく安心して自分らしく生きられるように「あなたの痛みに気づいているよ」「一緒に向き合っていこう」というメッセージを届ける存在でありたいと思っています。
子どもたちが、心から笑顔になれるように・・・
その願いを胸に、私たちは今日も診療に向き合っています。
南山病院
診療部 部長 森園 修一郎



